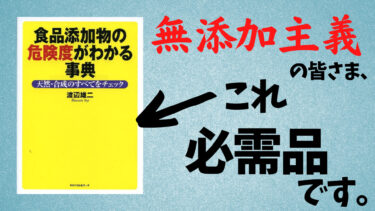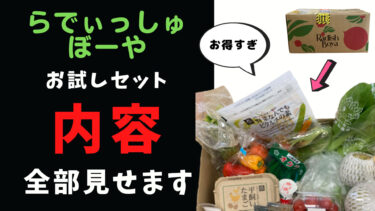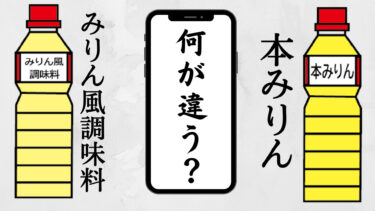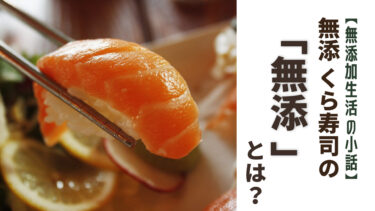ソルビン酸とソルビン酸Kってどう違う?
ソルビン酸やソルビン酸K(カリウム)、ソルビン酸Ca(カルシウム)は、保存料の中でも最も多くの食品に使われる食品添加物です。
使われている食品は、ソーセージ、ハム、かまぼこ、ちくわ、ジャム、漬物、チーズ、シロップなどなど。
これらの食品の保存性を高めるために、ソルビン酸が使われます。
食品業界に大きく役立っているのです。
しかしその一方で、様々な健康リスクが存在するのも事実で、個人的には出来れば摂りたくない添加物の1つです。
今回は、そんなソルビン酸について徹底解説していきます!
・ソルビン酸とソルビン酸Kの違いとは?
・ソルビン酸類を使うメリットとは?
・ソルビン酸類の危険性と使用基準は?
![]() 無添加の森管理人:yama
無添加の森管理人:yama
・持病(アトピー)改善のため、無添加生活を継続中
・日々、添加物について猛勉強中
・食品を買うときは、どこよりもまず裏を見る習性アリ
急いでいる方へ、先にまとめを出しておきます!
| 名称 | ソルビン酸(ソルビン酸K、Ca) |
| 分類 | 指定添加物 |
| 用途 | 保存料 |
| 使用例 | ソーセージ、ハム、ジャム、かまぼこなど |
| 安全性 | 危険 |
| 発がん性 | なし |
| 身体への影響 | 他添加物との相性× |
ソルビン酸とは

ソルビン酸とは、最も多くの食品に使われる合成保存料の1つです。
1955年にソルビン酸が、1960年にソルビン酸カリウムが食品添加物として認定されており、比較的古い添加物の一つです。
ソルビン酸カルシウムも近年認可され、以上の3つが使いやすい保存料として知られています。
用途・効果
ソルビン酸類は、基本的に保存料として使われています。
カビや細菌の繁殖を抑える作用(静菌作用)があり、腐りやすい食品の保存性を高めるうえで絶大な効果があります。
静菌作用とは、殺菌とは違って菌の増殖を抑えるだけなので、アルコールのように強い殺菌力を持つわけではありません。
ソルビン酸とソルビン酸Kの違い
特によく使われるソルビン酸とソルビン酸Kは、何が違うのでしょうか。
ざっくり言えば、ソルビン酸Kはソルビン酸にカリウムがくっついたものです。化学分野では、ソルビン酸Kのことを「ソルビン酸のカリウム塩」と表現します。
ソルビン酸Kは、ソルビン酸よりも水に溶けやすい特性を持っています。
そのため、ソルビン酸よりも圧倒的に使いやすく、より多くの食品に使われています。
化学物質というものは、カリウムがくっつくだけでも特徴ががらりと変わることがよくあります。
本当に化学って不思議です。
ソルビン酸とソルビット(ソルビトール)の違い
もう一つよく間違えられるのが、人工甘味料として知られるソルビット(ソルビトール)です。
ソルビン酸は保存料、ソルビトールは甘味料、なのでお間違えの無きよう…。
何故こんな名前が似てしまったかというと、名前の由来となった植物が同じだからです。
2つの名前は、ナナカマドという植物に由来します。
ソルビトールはナナカマドから発見された物質で、ソルビン酸はナナカマドの果汁に存在する物質です。
なので、ナナカマドの学名(Sorbus)から名前が付けられたのです。
ソルビン酸の危険性について

では、次に、ソルビン酸類の危険性についてお話しします。
ソルビン酸類は、危険な添加物として有名です。なぜなのでしょうか。
以下のような理由で危険視されています。
・変異原性がある
・他の添加物と使うと危険になる
動物試験の結果が不安
ソルビン酸に対して、動物を使った毒性試験を行った結果、以下のような結果が得られたそうです。
なお、以下は厚生労働省の食品安全委員会が発表した添加物評価書(|添加物報告書|厚生労働省 (mhlw.go.jp))を参考にして書いていますので、信頼性は十分かと思います。
・発がん性:無し
・試験管内の実験:染色体異常がみられた
このうち、腎臓重量は、ソルビン酸の毒性というよりもカリウムによる身体への影響と考えられています。
ただ、肝臓や精巣などに関しては、ヒトにも同じような現象が起こる可能性が無いとは言い切れないので不安です。
一方で、ソルビン酸類自体に発がん性は確認されていません。これは1つ安心材料になりそうです。
しかし、試験管内の実験で染色体異常が発見されたのが気になります。
ソルビン酸類は変異原性が認められる
試験管内の実験とは、動物の培養細胞株とソルビン酸を用いて試験管内で実験を行うことです。
つまり、実際の動物を使った実験ではありませんが、動物体内でも起こる可能性がある現象を知ることが出来る実験です。
ソルビン酸で見られた「染色体異常の発生」は、その物質が変異原性と呼ばれる性質を持つことを示しています。
変異原性は細胞をがん化する要因にもつながるので危険視されています。
この変異原性が、ソルビン酸にもソルビン酸Kにも認められたのです。
しかしこれはあくまでも試験管内のお話。実際の動物の体内では確認されていません。
ただ、それはソルビン酸のみに限った場合の話なんです。
他の添加物と使うと危険になる
ソルビン酸に発がん性の心配は無くても、私たちは他にも添加物を食べていますよね。
実は、ソルビン酸は他の添加物との相性がかなり悪いんです。
中でも気がかりなのが、ソルビン酸と亜硝酸塩との相互作用です。
ソルビン酸と亜硝酸塩を合わせて使用している食品には、ソーセージやハムなどの食肉加工品、他にも明太子などがあります。身近な食品が多いですね。
食品安全委員会の添加物評価書には、ソルビン酸と亜硝酸ナトリウムとの相互作用の試験結果も報告されています。
ソルビン酸と亜硝酸ナトリウムを合わせたものに毒性試験を行った結果、以下の3項目で陽性反応を示したそうです。
・小核試験
・染色体異常試験
「復帰突然変異試験」で陽性を示す物質は、高確率で変異原性を示します。
「小核試験」とは、染色体異常の原因となる小核の有無や出現率を調べる試験です。
小核とは、細胞分裂の際に異常が生じた結果、残存してしまった染色体の一部のことです。
いわば、異常が生じたことの目印なのですね。
特筆すべきなのが、「染色体異常試験」がマウスに経口摂取して行われたということです。
ということは、ソルビン酸単体では起こらなかった「体内での染色体異常」が起こってしまったということです。
3つの項目の結果からまとめますと、ソルビン酸と亜硝酸ナトリウムを合わせて使うと変異原性を示すようになるのです。
普段食べているソーセージやハムの裏側を見てください。
きっとソルビン酸と亜硝酸ナトリウムが使われているはずです。
ソルビン酸は保存料、亜硝酸ナトリウムは発色剤として欠かせません。
こうしてみると、個人的には、出来れば避けたい添加物の一つです。
ソルビン酸が安全だという主張
危険性を話してきた一方で、「そこまで危険視することは無い」という意見もあります。
実際、SCF(欧州連合食品科学委員会)では、ヒトに対する危険性は低いとしています。先ほどの毒性試験には相互矛盾があると指摘しており、信頼性に欠けるというのが理由です。
この辺は、科学が絶対に正しいとも言い切れないので、判断が難しいところではあります。
ですが、安全だと言えるのも「使用基準量を守れば」という前提があっての主張であることに間違いはありません。
ソルビン酸の使用基準

では、その使用基準についてみてみましょう。
| チーズ | 3g以下 |
| 魚肉練り製品、食肉製品など | 2g以下 |
| いかくん製品 | 1.5g以下 |
| 佃煮、漬物製品など | 1g以下 |
| ケチャップ、スープ、つゆなど | 0.5g以下 |
| 甘酒、発酵乳 | 0.3g以下 |
| 果実酒、雑酒 | 0.2g以下 |
| 乳酸菌飲料 | 0.05g以下 |
※参考:sorbic_detail.pdf (ueno-food.co.jp)
この値が使用基準ということは、1㎏当たりにほんの少ししか入っていないんですね。
この値を参考に、1日にどのくらい食べると危険なのかを調べてみました。
まず、ソルビン酸のADI(一日摂取許容量)は、25㎎/体重(kg)/日です。
これを体重50㎏の人に換算すると、1250㎎以上を1日に食べると身体に悪影響を及ぼす(可能性が高い)ということです。
1250㎎=1.25gです。
ソーセージを例に考えます。使用基準が1㎏当たり2g以下なので使用基準ギリギリまで使っていたとします。
市販のソーセージは1パック約90gなので、1パック当たりのソルビン酸の使用量は0.18gということになります。
つまり、体重50㎏の人が1日に食べて良いソーセージの量は、約7パックということになります。
そんなに食べる人はいないと思うので、そこまで心配する必要は無さそうです。
そもそも、使用基準量ギリギリ入っていることは珍しいです。
また、日本人の1日当たりのソルビン酸平均摂取量は13.6㎎と言われています。
これは、ADIの値の1.08%です。かなり少ないです。
日本で暮らす私たちが普通に暮らす分には、ソルビン酸はそこまで問題がないのかもしれません。
ですが、化学物質に敏感な人(アトピーの方など)は量に関係なく、症状が悪化したりする場合があるので、こういった合成添加物は控えた方が良いでしょう。
まとめ
さて、いかがだったでしょうか。
少し長くなりましたが、ソルビン酸について徹底的に解説しました。
添加物の歴史は浅いものです。動物試験の結果だけを見て「安心」とは言い切れません。
100%安全とは言い切れないからこそ「減らせるリスクは減らしておこう」というスタンスでソルビン酸に向かってみてはいかがでしょうか。
以下、大事なところをまとめました。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
では、また。
・【無添加生活に疲れたあなたへ】無添加生活を続けるコツ!無理しないための妥協法
・【月2万円】無添加生活にかかる食費を公開!食費を安くする方法!
・【体験談】アトピーに苦しむ僕が思う、無添加生活の効果と身体の変化
・「無添 くら寿司」の「無添」とは?添加物を使っていないの?
・【書評】無添加主義は『食品添加物の危険度がわかる事典』を読んでおこう!
・「みりん風調味料」と「みりん」の違いとは?どんな添加物が使われている?
・女性の白髪は【鉄分不足】が原因?やるべき対策とオススメの無添加鉄分サプリを紹介!
・ショートニングとは?危険なの?海外では禁止されている?【添加物徹底解説】
・【甘味料】スクラロースの危険性は?下痢になるって本当?
・ヤマザキが使用再開した臭素酸カリウムの危険性は?どのパンに入っているの?【添加物徹底解説】
[参考にしたサイト・文献]
・用途別 主な食品添加物 保存料|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)
・ソルビン酸についてー食環研 (shokukanken.com)
・静菌作用と殺菌作用、濃度依存型と時間依存型の抗生物質(抗菌薬) (kusuri-jouhou.com)
・変異原性 | 健康用語の基礎知識 | ヤクルト中央研究所 (yakult.co.jp)
・復帰突然変異試験(Ames試験) | ボゾリサーチセンター (bozo.co.jp)
・小核試験 | 顕微鏡観察ラボ | キーエンス (keyence.co.jp)
・|添加物報告書|厚生労働省 (mhlw.go.jp)