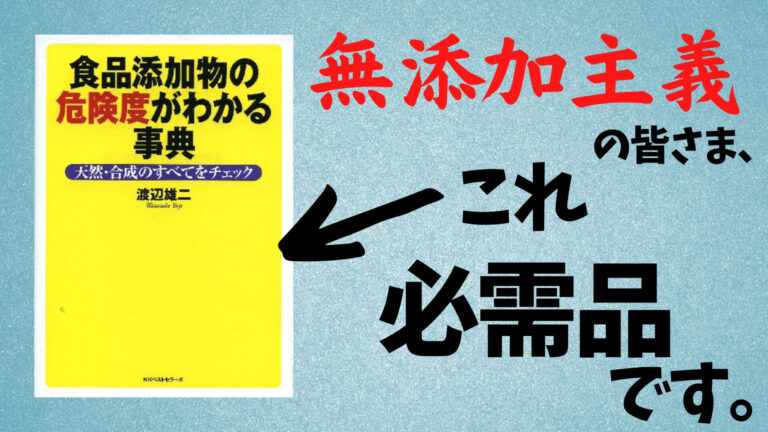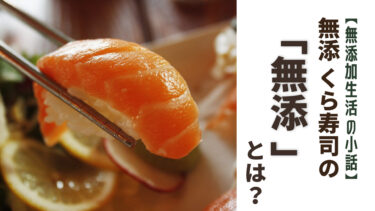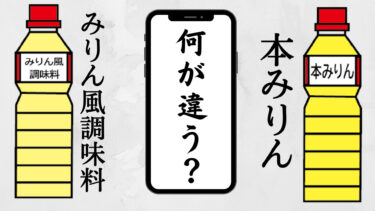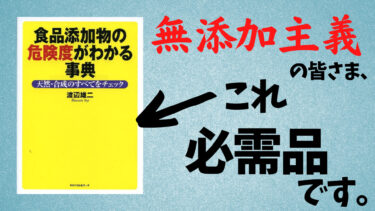こんにちは。
私は、持病(アトピー)の症状改善のため、無添加生活を続けています。
無添加生活とは、食品添加物を出来るだけ摂らない生活のことです。
私と同じように持病のため、あるいは健康のため、子供のため、色んな理由で添加物を控えている人に質問です。
こんなことを思ったことはありませんか?

僕も最初の頃は頻繁にこうなっていました(最近でもありますが)。そして、スーパーでスマホを開いてはいちいちググっていました・・・。
添加物の中には似ている名前のものがあったり、前に調べたものでも忘れちゃいますよね。
そんな時に役立つのが『食品添加物の危険度がわかる事典』です。
この本では、以下のようなことを知ることが出来ます。
・調べたい添加物が使われている食品
・調べたい添加物の危険度
つまり、無添加主義の方、添加物を避けたい方には、欠かせない一冊なのです。
実際、私も、バリバリ使っています。

『食品添加物の危険度がわかる事典』はこんな人にオススメ
『食品添加物の危険度がわかる事典』は他にもこんな方にオススメです。


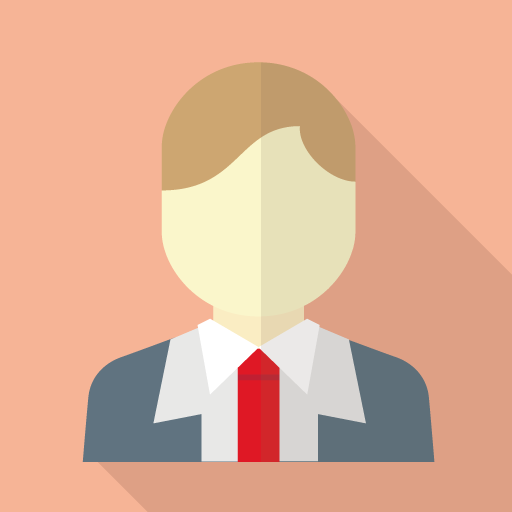

『食品添加物の危険度がわかる事典』の基本情報
この本の基本情報について説明します。
著者情報
渡辺雄二(ワタナベユウジ)
1954年生まれ。栃木県出身。千葉大学工学部合成化学科卒業。消費生活問題紙の記者を経て、82年に独立し、フリーの科学ジャーナリストとなる。以後、食品・環境・医療・バイオテクノロジーなどの諸問題を提起し続け、雑誌や新聞に精力的に執筆。とりわけ、食品添加物、合成洗剤、遺伝子組み換え食品などに造詣が深く、講演も全国各地で行っている
(BOOKデータベースより引用)
『食品添加物の危険度がわかる事典』を書いている渡辺雄二さんは、食品添加物に関する本を何冊も書いています。
科学分野の知識も深く、専門的な情報を提供してくれるイメージです。
過度に危険を煽るような文章ではないため、個人的には気に入っています。
添加物に対する考えは、人それぞれです。
なので、添加物関係の本では、著者によって添加物への向き合い方が変わってきます。
僕自身が読んで感じた渡辺さんのスタンスとしては、「危険性がゼロではないから、控えた方がいい」です。
内容
食品添加物の用途と危険度がこの1冊ですべてわかる。
(BOOKデータベースより引用)
内容は、本当にこの一言に尽きます。日本で使われているほぼすべての添加物が網羅されています。
目次
1 物質名で表示される化学合成添加物
2 用途名で表示される化学合成添加物
3 表示が免除される化学合成添加物
4 物質名で表示される天然添加物
5 用途名で表示される天然添加物
(BOOKデータベースより引用)
この本では添加物を「合成/天然」そして、「用途ごと」に調べられるように、分かりやすく分類されています。
甘味料、保存料など用途ごとにまとめられているので、めちゃくちゃ探しやすいんです。
もし、ただ50音順に並べてしまうと、色々な用途の添加物がごちゃごちゃになると思います。
評判
評判もあらかた良さそうです。以下にamazonのレビューをいくつか紹介します(引用元)。
評価:本書はコンビに・スパーで扱われる食品添加物の分類のみならず、人体への影響を解説し、危険度を5段階で表示してあるスグレモノである。実に見やすく構成されている。
欲をいえば、歯磨き粉に使用されている発泡剤、合成洗剤・家庭洗剤の界面活性剤等も載せて欲しかったが、枚数の関係によるのだろう。その点は続編を期待したい。
評価:ちょっとしたときにいつもこの本でチェックしています。
渡辺氏の著書はいろいろ読みましたが、これは一覧になっているのでとても見やすいです。
『食品添加物の危険度がわかる事典』のおすすめポイント

では、『食品添加物の危険度がわかる事典』のおすすめポイントを紹介します。
・添加物の基本情報を知ることが出来る
・独自の指標「危険度」が便利
調べたい添加物をすぐに調べられる
『食品添加物の危険度がわかる事典』では、事典と名の付く通り索引が付いています。
なので、調べたい添加物のページを一発で見つけることが出来ます。
また、添加物には、物質名は「アスコルビン酸ナトリウム」だけど「ビタミンC」と商品に書かれている場合もあります。
そういった表記のブレがある添加物でも、どちらの名前からでも索引出来るので便利です。
添加物の基本情報を知ることが出来る
索引から飛んできたページには、その添加物の基本情報が書かれています。基本情報の詳細は以下の通りです。
・危険度
・含まれる主な食品
・用途
・要注意ポイント
・人体への影響
「用途」には、何のために使われるか、が書かれています。
「要注意ポイント」には、その物質の情報や製造方法、添加物としての海外での扱いなどが書かれています。
「人体への影響」には、安全性を調べるための動物実験の結果やADIの数値などが書かれています。
これらの情報が1ページにまとめられているので、サクッと調べることが出来ます。
ググってもあまり情報が出てこないようなマイナーな添加物も載っているのも良いポイントです。
独自の指標「危険度」が便利
『食品添加物の危険度がわかる事典』の大きな特徴として、著者渡辺氏の独自の指標「危険度」が記されていることです。
この本では、各添加物を危険度1~5に分類しています。
・危険度1:安全性の高いもの
・危険度2:それほど気にしなくてもよいが、避けられれば避けたほうがよいもの
・危険度3:できれば避けたほうがよいもの
・危険度4:できるだけ避けるべきもの
・危険度5:極力避けるべきもの
(『食品添加物の危険度がわかる事典』から引用)
正直、動物実験の結果を読んでもよく分かりません。
そんな時に、この「危険度」という指標が役立ちます。
危険度を参考にして、自分で避けるべき添加物と許容できる添加物を決めることが出来るのです。
『食品添加物の危険度がわかる事典』を読んで思うこと
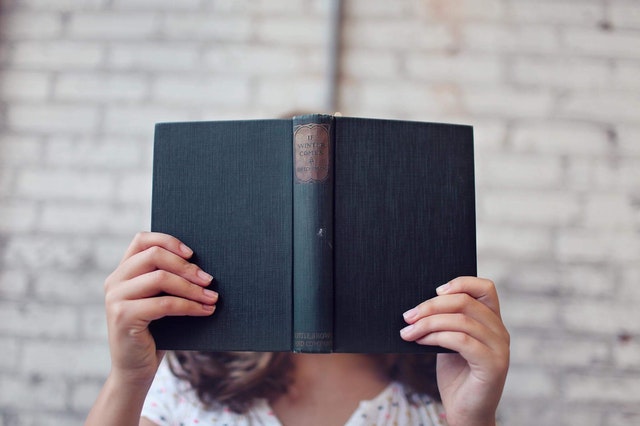
最後に、私の感想を述べておきます。
この本は、本当に「添加物の辞書のようなもの」です。
調べたい添加物に関する情報がすぐ手に入ります。添加物に気を付けている人にはとっても便利な本です。
しかし、だからといって「この本の情報だけをそのまま鵜呑みにするのはどうかな」とは思います。
この本には、動物実験の結果が情報として書かれてはいますが、その情報の出所は明記されていません。
なので、あくまでも「情報の1つ」としてこの本を使うべきだと思います。
これは、この本だけに言えることではありません。
ネットのサイト(このサイトも当てはまりますね)などでも1つだけ見るのではなく、色んな角度から情報を得て自分で学習・判断するべきだと思います。
色んな情報を調べて添加物を勉強するとして、この本は、最初にチェックすべき本です。
つまり、『食品添加物の危険度がわかる事典』は辞書のように「勉強のスタート地点」として活用することで、その効果が大いに発揮されるのです。
それは逆に、「この本を使わないと添加物の勉強が始まらない」とも言えるかもしれませんね。
まとめ
今回は、『食品添加物の危険度がわかる事典』についてレビュー・解説しました。
無添加主義の方がこの本を持っておいた方がいい理由が分かったかと思います。
そのくらい基本的なツールになると個人的には思います。
では、この本のポイントを最後にまとめておきます。
気になった方は、チェックしてみてください!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
では、また。
・【無添加生活に疲れたあなたへ】無添加生活を続けるコツ!無理しないための妥協法
・【月2万円】無添加生活にかかる食費を公開!食費を安くする方法!
・【体験談】アトピーに苦しむ僕が思う、無添加生活の効果と身体の変化
・「無添 くら寿司」の「無添」とは?添加物を使っていないの?
・「みりん風調味料」と「みりん」の違いとは?どんな添加物が使われている?
・女性の白髪は【鉄分不足】が原因?やるべき対策とオススメの無添加鉄分サプリを紹介!
・ショートニングとは?危険なの?海外では禁止されている?【添加物徹底解説】
・【甘味料】スクラロースの危険性は?下痢になるって本当?
・ヤマザキが使用再開した臭素酸カリウムの危険性は?どのパンに入っているの?【添加物徹底解説】
・ソルビン酸&ソルビン酸カリウムの危険性と使用基準は?【添加物徹底解説】